今年の終わりに
「第198回通常国会」のこと
―選挙の年に期待したかった国会審議のかたち―
ブログは年頭から休眠状態になってしまいました。思いついたことを書こうと思ってもなかなか困難ではありますが、年頭から精力的に集中したい関心事ができたことでブログから遠ざかってしまいました。ブログから遠ざかってほぼ一年が経ってしまいました。
そのうち、そのうちと思いつつ遠ざかってしまったのですが、今年の通常国会(第198回国会)冒頭の衆議院予算委員会の争点となった「統計問題」の専門性に嫌気がさしたわけではありませんが、委員会における問題の取り上げ方から委員会審議に関心が薄れていったことも遠因にもなってしまいました。
通常国会開会前に、賃金や労働時間の動向を把握する厚生労働省の「毎月勤労統計」の調査が不適切だったことがわかりました。通常国会の政局を左右する問題になるかという見方もありました。しかし、委員会での審議が進むにつれ、野党が、政権批判の政局化という方向からこの問題の議論を進めても夏の参議院議員選挙を控えた国会において与野党の対立軸として争点化できる性質のものではないのではないか、このままの展開では、選挙前の国会の議論を国民に知ってもらうという最高の機会を生かし切れない、来るべき選挙に国会の議論を通じて対立軸、争点を提示できないのではと思ったことから委員会審議に関心が薄れてしまいました。
(「毎月勤労統計」の不正調査問題のだいたいの整理としては、第198回国会召集前の、1月に開会された衆議院厚生労働委員会の閉会中審査の委員会から議論がはじまり、第198会国会において引き続き予算委員会冒頭から野党はこの問題を集中的に取り上げ、「アベノミクス偽装」、「官邸関与」と追及しましたが、政権のほうは陳謝しつつも厚生労働省の責任だとし、アベノミクスの成果を強調するという展開で推移しました。そして議論は盛り上がりを欠いたまま与野党は統一地方選や夏の参院選に向け、「選挙モード」に入って行ったという印象でした。審議も堂々巡りで、予算委員会で政権を追い込むということも難しく、野党は「毎月勤労統計」の不正調査問題を参院選の足がかりにしようとしたものの、前半国会は尻すぼみに終わったということだったと認識しています。)
国会で行われている議論は、一般の国民はテレビ、ラジオ、新聞などの報道によってしか知ることができません。通常国会では統計問題以外の国政問題、税制、外交、安全保障問題も議論されています。しかし、それらは報道されなければ一般には知らされません。またどのように報道が取り上げるかによってわれわれ報道される側の受け取り方も変わってきます。税制、外交問題等の問題も報じられてはいましたが、予算委員会審議の進展につれ、報道の取り上げ方も統計問題一色に見え、国会では統計問題ばかり議論をしているという印象が私には強くなりました。そして統計問題の報道も記事内容が次第に複雑になり、もともと統計に詳しいか、今回の統計問題に特に深い関心があるかでないと、国会での議論を中心に報じる報道内容の進展についていけない気がしました。日常的に政治の世界にいない人たちは、議論の展開をわかりやすく理解しづらかったのではないでしょうか。(「統計」関係の知識がなく日常的に関心も薄いことなどから、私自身の、統計問題に対する本質的問題性認識の貧困から感じることかもしれませんが。)
そもそも、国会の議論を通常は報道でしか知ることができない一般国民に対していかに知らせるか、何を報道させるかを議員のほうも意識した論戦が必要ではないでしょうか。(テレビ中継されている審議で多くの国民が視聴していることを意識して、過大に政権批判、野党批判、揚げ足取りなど自党の誇大宣伝、対立党のマイナスイメージの拡散などにこだわることとは別の次元の問題として。)
特に選挙を控えた年の国会はそうでないときとは論争の性質は異なると思います。与野党の対立軸、争点を明確に国民に示していかなければならないと思います。「常在戦場の心構え」という言葉は政治家がよく使う言葉ですが、本来はそういう気構えで与野党の対立軸を明確に国民に示すことが国会論争の基本だと思います。毎国会、おなじみと揶揄されることもある内閣不信任案提出で対立軸を示しているという見方もあるのかもしれませんが、、、、。
繰り返しになりますが、今年は夏に参議院議員選挙が控えていました。選挙にあたって、政党は「何が政治の争点か」を有権者に提示することが重要であり、責務でもあります。多くは選挙公約、選挙演説などでしょうが、まさに選挙直前まで開会している通常国会は、与野党ともに「何が政治の争点となっているか」を国民に対して明確にしておかなければならない、選挙公約、選挙演説に勝るとも劣らない重要なステージではなかったのでしょうか。
しかし、今年の通常国会における論争の口火を開く予算委員会を舞台にした議論の中で、統計問題が中核的な争点として位置付けられたと理解していますが、予算委員会審議を通じて何が見えてきたのでしょうか。参議院議員選挙を夏に控えて、与野党の対立軸を明確にする契機となったのでしょうか。政権に挑む立場としての野党は、何を選挙で国民に問うのか、与党との対立軸を明確にできる争点を国会という場を通じて、国民に明確に示すことができなかったのではないかと私には思えました。選挙公約を読めばわかるという次元の問題ではないと思います。立法府の構成員である議員の活動の最も根源的な公的活動の場である国会における議論という形で国民に示すことが基本だと思います。こうしたことから、個人的な問題意識の持ちようかもしれませんが、国会における議論から積極的関心が薄れてしまいました。
統計問題は、不正か違法か、事務的ミスであるのかなど国会の行政監視機能が発揮できるかどうか、大事な問題でありました。国会冒頭から統計問題に対して野党も積極的に追及しなければなりませんでした。この問題を選挙を控えた政治の争点のポイントとして位置付けることもできるのかもしれませんでしたが、委員会での審議が進むにつれ、政権追及型ではなく行政是正指摘型の問題として議論をまとめる方向で対処して、予算委員会審議の限られた日程のなか、選挙で争点としたい他の問題をさらに国民に印象づけ提起していくことが必要ではなかったのでしょうか。
の政治的争点、対立軸を提起していくのか。





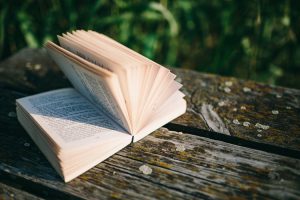













最近のコメント