国会改革……何を改革するのか。
国会改革について小泉議員を事務局長とする自民党プロジェクトチームと立憲民主党の動きがあります。
小泉議員サイドの主な提言は「党首討論の定例化と夜間開催」、「タブレット端末の導入などによるIT化推進」、「女性議員の妊娠・出産時の代理投票」など、立憲民主党の提言は「議員提出法律案を質疑する定例日を各委員会に設ける」、「衆参の予算委員長を野党議員のポストにする」、「党首討論の時間の延長」などと報道されています。
国会改革をテーマにしたのは、現在の国会で改革すべきものがあるとすれば何か、そしてその理由や改革の目的などについて考えてみることで、議会政治の現状と課題が把握できるのではないかと思うからです。改革のなかでも、国会において長く継続されてきた形式の変更や予算を措置することで可能になるものなど、与野党で合意できればいつでも可能な改革もあるでしょうし、急いでやらなくてもよいもの、現状のままでも支障は生じないものもあると思います。そのような改革から離れて、ここでは、議会の権能、機能に「実質的」にかかわる改革とは何か、その「実質的改革」の可能性と困難性を考えてみます。そのほうが議会政治の現況をよく把握できると思うからです。
議会政治の形骸化が指摘されることがあります。議会政治のどこが形骸化しているかについては、与党、野党の間、政党間で認識がすべて一致するものではないかもしれません。国民レベルでも、いわゆる知識人とされる人たちの間でも様々な立場から認識が一致するものではないかもしれません。そのことを前提とした上で、議会政治の形骸化とその改革という視点から議会政治の現況を考えてみます。
議会は形骸化しているのか。国会審議についての評論、報道などでは「議案審議の形骸化」や「国政調査権の実効性の問題」が指摘されることがありますが、ここではひとつの例として、国政調査権の実効性の問題として「議会による行政統制の形骸化」について考えてみます(「行政統制」、「行政監督」、「行政監視」を同じ内容を意味するものとし、主に「行政統制(機能)」として表記します。)。具体的には、議会の行政統制機能の行使とそこに潜む厄介な問題ということから、実質的な国会改革の可能性と困難性について考えてみたいと思います。1)「議会による行政統制の形骸化」を是正する「改革」として、政府・行政権との関係で議会の地位を確立することを目的とする制度改正(平成11年)がおこなわれましたが、実効性のある国会審議活性化改革になり得たかどうか(議会における本会議、委員会の審議過程等が実質的に改革できたのか)について検討してみる必要があります。
(「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成11年7.30 法律第116号)」(国会審議活性化法)の趣旨は、国会における審議の活性化、行政機関における政治主導の政策決定システムを確立することとされ、これによる政府委員制度の廃止、副大臣、大臣政務官の設置、党首討論の新設などが定められた。)
国政調査権は、議院が「広く国政、とくに行政に対する監督・統制の権限を実効的に行使するために必要な調査を行う権限」(野中ほか・「憲法Ⅱ第5版」143頁)で、「行政全般にわたって調査権を行使でき(中略)国政調査権が最大に機能するのは、この場においてである」(浅野一郎・「議会の調査権」95頁)と説明している学説があります。
行政統制機能の法規上の手段としては、主に議院の委員会において政府当局からの説明聴取、質疑、資料の提出要求、証人として出頭要求、書類の提出要求などです。この権能の行使によって情報収集を行い、国民に対し明確な争点を提示し、行政の方針に対し代案の提示を可能にするなどのための議会の有する大きな機能ですが、そのための機能が十分に発揮できていない、「議会による行政の統制機能が形骸化」しているのではないかとの批判もあります。この指摘を考えてみますと、議会政治がそのような状況にあるのは「政府・与党」の構造強化2)行政に対する立法府という図式のなかで、与党と政府の結びつきが強化された結果、「政府・与党」間で「行政府vs立法府」という緊張感が緩くなっている関係。が進んでいることから、行政に対する議会の権限行使は、事実上、主に野党によって行使されるケースになることが多くなると考えられ、それには多数党としての与党の賛同がなければ実現困難であること、しかし、現実の国会運営において、「政府・与党」という関係から多数党である与党は行政に対する国政調査権行使による行政監督に消極的になる傾向が強く、そして、政府の意を実現する機関としての多数党として存在せざるを得ないということなども背景にあるかと思います。3)議院内閣制における内閣と与党の関係について次のような見解がある。(第139回国会 参議院行財政機構及び行政監察に関する調査会第1号(12頁)、清水睦中央大学法学部教授)「そうなりますと、ただいま御質問がございましたように、委員会の意思決定というのはやはり多数決でなされると多数党の 意思が委員会の意思になっていく。そうしますと、多数党というのは通常与党でございますから、与党の意思で実際の運営がなされると政権党の意思が物を言うから、結局時の内閣のもとにある行政に対して効果的な国政調査権の行使が望めないのではないかという、そういう御疑問であったかと思います。しかし、原則的にはそれは私はやむを得ないことなのではないかというふうに思います。議院内閣制というものは、やはり与党を含めたハウス、国会、これが行政、政府を一応監視するという建前になっているわけですから、その建前は建前として、実際それでは効果が薄いというふうなことを考えれば、野党に行政に対する監視の重要な権限である国政調査権につきイニシアチブをとらせるという配慮を多数党自身がなすべきである。それをやはり一定の法規の形で保障を明確にするということが与党の雅量といいますか、与党が議院内閣制を憲法上のあるべき姿で運営していくという場合にはそういう態度が望ましいわけであって、これは憲法がその条文でそういうことを定めてはおりませんけれども、法 律、規則等でそういうことを定めることは可能であり、そのことは別に憲法上の議院内閣制に反するわけではございませんの で、そういうふうなことが重要であると思っているわけでございます。」
確かに、与党が野党と同じ方向で行政府に対峙すれば行政統制機能は円滑に機能し、内閣提出法律案審議においても実のある政府の追求が可能になり、議案の否決、修正という形で立法府の意思を反映しやすくもなり、その点からは、立法機能、審議機能などが充実したものにはなるでしょうが、そのようなことを、現在の議院内閣制における「政府・与党」の関係で存在する与党に期待するのは、現在までの国会の歴史的経緯からは、むしろ「間違った期待」であると考えることもできるのではないでしょうか。
また、議案審議において、与党はなるべく早く成立を図ろうとするため、議案の目的等によっては野党の意向をさほど取り入れることもなく審議時間・日程を可能であれば短くする傾向にあり、このことが審議形骸化の大きな原因であるなどとして批判されています。しかし、質疑時間等を野党の要求どおり実現したとして、それだけで充実した審議が可能でしょうか。審議時間が増えることが充実した審議になるのでしょうか、それで結果は変わるでしょうか。野党が反対する議案を否決、修正することが可能でしょうか。議案の質疑、討議の過程で野党は与党を野党の考えの方向に説得できるでしょうか、また政府の答弁次第で野党は議案に対する態度を反対から賛成に変更する用意ができているのでしょうか。議院法規では討論や修正などの審議手続が規定されていますが、野党の意向で与党の態度が変更するような審議が可能であったことはほとんどないのではないでしょうか。議案審議において、争点を明確にし、議案の問題点を明らかにし、必要があれば修正案を提示しながら、妥協点を見出していくという充実した審議が現在の議会政治で可能かどうかということを考えてみることも大事だと思います。
上記で述べたことについては、「議会において与党が多数を占めている状況下では、内閣提出法律案の審議時間・日程がどの程度であるかにかかわらず、議案を提出した段階でその議案の可決・成立の結果が見えている。したがって、審議時間を多くとるなどの「形式的な審議充実」をはかっても意味がない」などという「なげやり」的な考えからではありません。会議において議案審議を行うことは可否の結論を出すことだけでなく、その過程でどのような質疑でどのような政府答弁を引き出すか、議案に対する賛否とは別に内閣提出原案の条文のなかに見過ごせない誤りがあれば明確にすべきであり、そしてそれを会議録に残すということは議会における議案審議機能の重要なところであります。議案の内容によっては、いわゆる「対決法案は」、内閣から提出される前から野党の態度(反対)が決まっていることがほとんどだと思います。このような場合、議案の審議は、ある場合は修正を求めるときもあるでしょうが、大体にして議案の継続審議、廃案に向けた、議案審議過程はそのための議論の展開になります。このようなとき、それを「反対のための議論」、「反対するだけでなく、対案を示せ」、「決める政治ができない」と批判する見解もあります。しかし、反対のための議論も議会政治において重要なことであるのはいうまでもありません。反対の議論をして、争点を明確にして国民に提示することも野党の義務であるでしょうし、その争点、問題点などの議論を会議録に残しておくことは議会政治の譲れない機能だと思います。この点からは十分な質疑時間が保証された充実した審議の実現は、議会形骸化是正のための重要な課題であることはいうまでもありません。また、現在の議会政治のなかで、野党は政権交代を目指すためにはその土俵である議会審議の場で現政権の欠陥等を明確にすることが「義務」であるため、その義務を果たす意味でも充実した審議の場の確保を求めることは当然であり、与党の強引な議会運営に対して日程闘争、物理的な抵抗をすることは野党の権利だと思います。(以上のことについては、混乱を避けるために、ここでは別の次元の課題とさせていただきます。)
議会形骸化の原因は多岐にわたりますが、与党だけに原因があるわけではなく、与党の数の横暴だけを過大に批判しているだけでは本質的な問題を見失うような気がします。野党にも問題があるのではないでしょか。無力、無気力、抽象的な批判、核心をつけない質問、マスコミ情報に依存する情報収集能力の貧困、そして政権交代への展望を示すことができないなど厳しい状況です。
議会形骸化を是正するには困難な課題があります。多岐にわたる形骸化是正を実現していく議会の土俵つくりの前提には、議会の権能の発揮を牽引する野党の役割を果たす「期待に応えられる野党」の存在が必要であり、さらにはそのような野党の役割を受容できる与党の存在が必要であると思います。ここに国会の実質的改革の困難性の問題があるのではないでしょうか。
しかし、現在の政治状況のなか、「敵に塩を送る」ようなことを一方的に多数党である与党に望むのは無理な話です。議会は政党が次の国政選挙に向けた与野党の「対立構図」を国民に示す重要な場でもあります。
現状では不可能に近いかもしれない国会の実質的改革の可能性は、与党と野党の新たな関係、議会政治における政党の在り方の変化、そしてそれを可能にする「制度的状況の出現」が俟たれるのかもしれません。この実質的改革の実現に向けては、抽象的でありますが、「相互的寛容」、つまり政党間でお互いを正当な対抗者として受け容れるという「規範」が前提になるのではないかと思います。
議会の形骸化の改革は、一例を挙げれば、選挙制度の改革にもひとつの可能性を期待することができるかもしれません。「政権交代可能な政党システムの実現」、「二大政党」か多数党の存在のなか「連立政権」が望ましいのかなども論点になってくると思われます。言うまでもなく議会形骸化の原因がひとつでない以上、選挙制度改革だけで議会形骸化是正が実現できるはずはありません。立法機能、審議機能、行政監督機能の形骸化、議会の形式機関化など広い範囲に機能低下が指摘されており、国会のなかだけの「現状変更」だけでとても実質的改革ができるものではないと思います。
長い内容になってしまいました。「議会は形骸化しているのか」、その視点から、議会の現状と改革の困難性などについて、(非常に難しい問題であり、力の及ぶところではありませんが、)引き続き考えていきたいと思います。
References
| 1. | ↑ | 「議会による行政統制の形骸化」を是正する「改革」として、政府・行政権との関係で議会の地位を確立することを目的とする制度改正(平成11年)がおこなわれましたが、実効性のある国会審議活性化改革になり得たかどうか(議会における本会議、委員会の審議過程等が実質的に改革できたのか)について検討してみる必要があります。 (「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成11年7.30 法律第116号)」(国会審議活性化法)の趣旨は、国会における審議の活性化、行政機関における政治主導の政策決定システムを確立することとされ、これによる政府委員制度の廃止、副大臣、大臣政務官の設置、党首討論の新設などが定められた。) |
| 2. | ↑ | 行政に対する立法府という図式のなかで、与党と政府の結びつきが強化された結果、「政府・与党」間で「行政府vs立法府」という緊張感が緩くなっている関係。 |
| 3. | ↑ | 議院内閣制における内閣と与党の関係について次のような見解がある。(第139回国会 参議院行財政機構及び行政監察に関する調査会第1号(12頁)、清水睦中央大学法学部教授)「そうなりますと、ただいま御質問がございましたように、委員会の意思決定というのはやはり多数決でなされると多数党の 意思が委員会の意思になっていく。そうしますと、多数党というのは通常与党でございますから、与党の意思で実際の運営がなされると政権党の意思が物を言うから、結局時の内閣のもとにある行政に対して効果的な国政調査権の行使が望めないのではないかという、そういう御疑問であったかと思います。しかし、原則的にはそれは私はやむを得ないことなのではないかというふうに思います。議院内閣制というものは、やはり与党を含めたハウス、国会、これが行政、政府を一応監視するという建前になっているわけですから、その建前は建前として、実際それでは効果が薄いというふうなことを考えれば、野党に行政に対する監視の重要な権限である国政調査権につきイニシアチブをとらせるという配慮を多数党自身がなすべきである。それをやはり一定の法規の形で保障を明確にするということが与党の雅量といいますか、与党が議院内閣制を憲法上のあるべき姿で運営していくという場合にはそういう態度が望ましいわけであって、これは憲法がその条文でそういうことを定めてはおりませんけれども、法 律、規則等でそういうことを定めることは可能であり、そのことは別に憲法上の議院内閣制に反するわけではございませんの で、そういうふうなことが重要であると思っているわけでございます。」 |






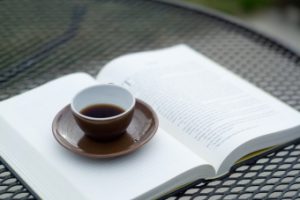












最近のコメント