前回に続き、議会形骸化に関連した内容です。
12月10日に閉会した第197回国会では「出入国管理・難民認定法改正案」(「入管法改正案」:以下同じ。)が争点になりましたが、衆議院における審議のなかで気になったことがあります。
いくつかの報道で、「入管法改正案」の審議において与党が強引な議事進行を繰り返したと指摘し、それが国会空洞化の深刻さを現すものだと与党を批判する記事がみられましたが、果たしてそういう批判が「空洞化の本質」をついているのか、与党だけの責任なのかについて考えてみたいと思います。それは議会形骸化の是正を考えるとき、与党だけを批判するだけでは解決しないのではないか、という考えからです。
「入管法審議」のなかで、委員長の職権によって開会日時が決定され審議が行われました。委員会の定例日でない日についても職権で開会されましたが、これに関して委員会運営上の問題としてはどうであるか考えてみたいと思います。また、新聞情報によれば、委員長職権で委員会の定例日でない11月22日(木)に委員会を開会し、さらにまた定例日でない26日(月)の開会を決定したことについて、立憲民主党など野党4党派(一部野党は除く)は日程ありきだとして反発、定例日を無視した強行に野党側は態度を一段と硬化などと報じています。委員長が職権で開会日程を決定するということは、事前の理事会における与野党協議で合意が得られていない、野党(全野党または野党第一党を含む複数野党会派の場合や野党第一党だけの場合をいう。以下同じ。)が反対している、あるいは野党が反発して理事会に欠席しているなどという状況であろうかと思います。合意があるのならば「委員長職権」といわれる「委員長権限の行使」ということをわざわざ表立たせる方法をとる必要はないわけですから。通常、そのような場合、野党は反発して委員会を欠席することが多いかと思われますが、野党が反発する状況下で定例日でもない日に委員長の職権で開会された委員会に、その反発した何らかの事情がいくらかでも解消されたのならともかく、解消もされない状況のなか、野党が委員会に出席・質疑したことについても、何故なのか、どういう行為と考えればよいのかなど考えてみたいと思います。
まず、委員長の問題として、委員会開会日程について野党が反発しているなか、「定例日以外の日」に開会することを職権(権限)で決定したことについてです(委員長職権で定例日にも開会されていますが、ここではその点については問題にしません。)。
委員会の開会について、衆議院規則67条1項は「委員長は、委員会の開会日時を定める。」と規定し、委員長の開会日時決定権を定めていますが、実際には委員長が理事会で協議した上、決定されています。理事会などの場において与野党合意が得られていないときなどに、委員長が委員会の開会日程を決定し委員会を開会することを「委員長の職権開会」と言っていますが、ここでは、委員会の開会は委員長の職権(権限)であるのでそれ自体は法規上、形式的には問題ないものとしておきます。そのうえで、委員長の職権開会が問題にされるのはどのような場合か、について考えてみます。
議会運営に関する事項は、憲法、国会法、議院規則などの議院関係法規に定められていますが、それらの成文法だけでは、議会運営のすべてを網羅できるものではなく、議会先例がそれを補う役割を果たすものと位置づけられています。議院には「先例集」として編纂されたもののほか、各会派の「申し合わせ」などの合意も含め、議会運営において長年にわたり積み重ねられてきたものなど明文化されていない、委員会運営の「準規則的」なものとして理解されているものがあると思います。
委員会の定例日についてもそのようなものではないでしょうか(定例日を設けていない委員会もあります。)。定例日については法規上の規定はありませんが、国会の本会議や委員会は、それが開会される場合には毎週決められた曜日に開かれるのが慣例になっており、この日を定例日と称しています。当初は「常任委員長会議」という会議体で各委員会の定例日が定められていたようですが、やがては定例日を定めず委員長が必要に応じて開会するという運営になり、その後また定例日が復活し、今日のようになっているようです。委員会の定例日は当該委員会の理事会の与野党協議を経て定められ変更も可能なものですが、「委員会は定例日を設ける」という合意は当該委員会の「先例的運営方針」ともいえるものではないでしょうか。
そのような理解で、委員長職権による委員会開会のうち、委員長が定例日でない日に職権で委員会を開会したことについては、与野党の協議で決められた「定例日開会という運営方針」があるにもかかわらず、開会日程について野党の反発(注:反発という表現は、新聞情報なので実際の状況などはわかりませんが、通常、反発しているということは同意していないということであろうと判断します。)があるなかで決定したという点において、法規上の問題はないにしても、委員会における「先例的運営方針」が遵守されなかったということで、委員長の職務権限行使に関し「運営上の問題」があるとの批判が生じる場合もあるかもしれません。委員長職権の行使が問題のあるものであるかどうかは、そのときの委員会を構成する各会派の考えや委員会がおかれている諸状況などから判断されるもので機械的に判断できないものだと思われます。運営上問題があるとされた事案と同様の事案がその後生じた場合でも、先の事案と同様に運営上問題あるものと判断されるかどうかはわからないというような性質のものではないかと思われます。しかし、委員会の定例日あるいは定例日外の開会であろうと、野党の同意がないからということだけで委員長の権限行使が無条件に批判されるものではないと思います。それが問題とされるのは開会日程を決定し委員会を開会するに至る背景は何だったかにもよると思います。
定例日外開会については、日程上の都合などにより委員会を開会する必要が生じることもあると思います。その場合には、定例日外の開会が与野党合意のもとであることが先例的前提であることは言うまでもないと思います。また、審議拒否などの日程闘争と会期の残り日数の関係からやむを得ない事情があると認める場合や、恣意的な審議日程妨害(何が恣意的妨害かの客観的認定は困難ですが)を避けるなどのために委員長が必要であると判断する場合には、定例日あるいは定例日外の委員長職権による開会は委員長職権(権限)の正当な行使として考えられることもあるかと思います。
次に、野党として委員会開会に同意できなかったことの問題が何も解消されていない(与党の採決ありきの日程が修正されていない)なか、委員長の職権で開会された委員会に出席したことについてであります。報道で知る限りで、素直に考えたとき、何故出席したのかよくわからない行動です。
11/22(木)、26(月)、27(火)の職権開会では、政府に対する質疑が行われています。定例日でない22日に行われた政府に対する質疑には野党は欠席しましたが(同日の参考人質疑には野党は出席し質疑)、26日は定例日ではありませんが出席して政府に対し質疑を行っており、27日には法律案の採決が行われています。
定例日あるいは定例日外であろうと、委員長の職権開会となった委員会に野党は反発(通常、野党としては開会に同意していないと推測される)していたというのに、出席して質疑を行ったのは何故なのか、報道からの情報ではその事情がわかりません。野党としては開会日程自体に反発しているなかでの職権開会に対しては何らかの妥協や意向がかなうなどの成果が得られなければ、まして定例日外の職権開会でもあることから、抵抗することが「建前」ではないかと思います。(定例日外の26日(月)には午前、午後にわたり衆参の予算委員会が開会され「内外の諸情勢」について審議が行われ、その終了後に法務委員会は開会していますが、衆参予算委員会開会が野党側の成果として法務委員会の質疑に応じる形となったのでしょうか。)建前のための抵抗は、「反対のための反対」、「対案なき反対」などとして批判されるからでしょうか(それが全く意味がないとは思いませんが)。かりに建前のための抵抗をやめたとしても、それでは何故、委員会の開会に反発したのでしょうか。与党サイドの方針として、採決ありきの日程が前提にあったからでしょうか。委員会には出席して質疑は行うが、日程上採決ありきの前提としての開会自体には反対の意思を明確にしておくということだったのでしょうか。わかるような気がしますが、あえて問題点を探してみなければならないような気がします。報道では熟議が保証されなかったとして与党が批判されますが、熟議を志向する野党の存在も必要だからです。
「入管法改正案」審議に関連して10日間ほどの会期延長が国会召集冒頭から与党関係者から言われていました。しかし、政府、与党は予算編成などのためできれば早めに国会を閉じたいでしょう。野党は早く国会を閉じたい事情があったのでしょうか。そうでなければ数日でも法律案の成立を遅らせるよう抵抗することは野党の通常の方針になるのではないでしょうか。どうせ成立するのだから「無駄な抵抗は非生産的だ」とでも考えるべきなのでしょうか。わかる気がしますが、その「無駄だと思える抵抗」が必要なときもあるのではないでしょうか。
職権開会を含め強引な議事運営をしても野党はついてくると与党が思うかもしれません。これが契機となり、与党が今後の運営についても強引な議事運営にむかったとき、議会審議における熟議が遠のくばかりであり、そうさせた野党の責任もあるのではないかという批判を容認しなければならないと思います。この点からは、野党は熟議をもとめる姿勢を放棄したのかと受け取られてもやむを得ないところがあります。内閣不信任案、大臣不信任案、常任委員長解任決議案などを提出して会議で与党を糾弾することも大事なことであるとは思いますが、無駄な抵抗で非生産的だと思われるものでも必要とされるものもあると思うのですが。
熟議の審議を求める一環で、欠席などによる日程上の抵抗の形が何故とれなかったのでしょうか。審議拒否、欠席戦術が「抵抗だけの野党」だとして批判されるからでしょうか。野党の対応は与党の横暴さを強調しただけであり、結局はそれが目的だったのかと推測されるかもしれません。そうしたことは、次期選挙を念頭にした戦術として政党には必要な場合もあるかもしれません。しかし、熟議を志向する姿勢(現在の政治状況下では無駄な抵抗であるかもしれませんが)を放棄して与党の横暴さを強調するための戦術をとったとみられることもやむを得ないかもしれません。
また、いわゆる日程闘争ばかりで無駄な抵抗をしている、抵抗・反対するばかりで対案を提示できないなどと批判され、そうしたことが「決められない政治」の一因とも批判されることがありますが、そういった「決められない政治」批判を恐れることから、従来からの抵抗をやめることが、場合によっては「熟議」の道を閉ざすことになるのではないかと思います。
無駄な抵抗も政権与党を疲労させる効果はあると思います。疲労回復のためには野党の話を聞く必要があるかもしれません。そうなれば「無駄な抵抗」も無駄ではなくなります。「うるさい方々」であることは、数の力で劣る野党の武器でもあるのではないでしょうか。
いわゆる「決められない政治」、「抵抗野党」批判を免れるために、議会政治における少数者の抵抗の形を野党から無条件に放棄すべきではないかもしれません。議会政治においては、たとえば議案審議に際して、与野党は議会としての「審議の形」をつくることが必要ではないかと思います。結論がみえているのはわかっていても審議を重ねる努力をし審議の「形」をつくる、無駄な抵抗でも抵抗してその「抵抗の意思」を審議拒否、欠席するなどの手段で「形」として表し残しておく、参考人質疑を行う、公聴会を行う、地方公聴会を行う等々、審議の「形」をつくれるものがあります。審議の「形」を残し、それが会議録等で残っていくわけですからそこで行われた質疑応答の記録は議会の財産になるのではないかと思います。野党の役目を果たす野党の誕生が求められると思います。
野党のレベルがさらに上がれば与党にも影響し、さらに与党のレベルが上がるでしょう。しかし、与党のレベルが上がらずに、野党がさらにレベルアップすれば政権交代になってくる可能性もでてくるかもしれません。選挙対策からは出てこないレベルアップもあるのではないでしょうか。
議会形骸化、空洞化は野党の在り方にも原因があり、ただ与党だけを批判するだけでは解決しないのではないかと思います。
(補記)
今回、法務委員長(衆議院)は早い時期に「解任決議案」が提出され否決されました。常任委員長解任決議案が否決されれば同一会期では解任決議案を再提出できないというような理解があるようで、以後、その委員長は、自由に思うがままに議事運営できる、いわゆる「スーパー委員長」と評する向きもあるようです。「議案」と「委員長(委員長の職務権限)」では一事不再議における質的相違があると思います。機会があれば考えていきたい課題です。



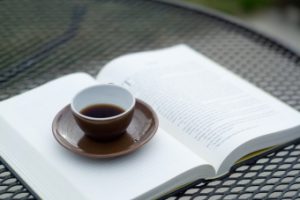















最近のコメント