前回に続き、第197回国会における「出入国管理・難民認定法改正案」(入管法改正案)の衆議院における審議に関連したテーマになります。(長くなります)
「入管法改正案」の衆議院議決に際し、衆議院議長が立憲民主党などの野党に示した議長提案(報道では「議長裁定」、「議長仲裁」という用語も使われていますが、ここでは「議長提案」とします。以下同じ。)について考えてみたいと思います。
「入管法改正案」は委員会において4回の審議が行われています。いずれも委員長職権で開会されたものでした。このうち2回は定例日外で、野党は、審議時間が十分でなく採決ありきの日程であり、法律案の内容には、制度について改正案成立後に省令で定める事項が多いことから「白紙委任だ」などと批判していました。11月27日の委員会採決後(与党が立憲民主党などの野党の反対を押し切って採決。自民、公明、維新の賛成多数で改正案を可決した。)、立憲民主党など野党6党・会派の国会対策委員長から大島衆院議長に本会議採決を見送る旨の申し入れがあった後、大島議長は自民、公明の国対委員長と国会内で会談を行い、与党に改正案の施行前に運用方針や関連政省令を国会に報告するよう求めました。この大島議長のあっせんを野党は受け入れ、衆院本会議での同法改正案の採決に応じました。その後、大島衆院議長が、入国管理法改正案の施行前に、政府から政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告するよう求め、そのうえで委員会において質疑を行う旨の議長提案を示しました。この提案に対し立憲民主党など野党は議長提案を評価しました。
議長提案の内容は次のようです。
「入国管理法改正案について(議長発言要旨)…本案については、関連する分野及び政省令事項が多岐にわたると指摘されている。議長としては、入国管理法改正案の施行前に、政府から政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告していただきたい。そのうえで、次期常会の適切な時期に、法務委員会においてその報告に対する質疑ができる環境を与野党間で調えてもらいたい。もって、法制度の全体像について、国民に知らしめ、その理解をいただきたいと思う。」(立憲民主党ネット情報から)
1 上記の議長提案の文面からでは、提案の意味するところが奈辺にあるかはわかりません。議会審議機能等の向上に質するものとして前向きに捉えることもできますし、与野党の膠着した事態打開の策として捉えることもできるでしょうが、そこはわかりません。報道等で知る限りですので確認はできません。
そこで報道記事のなかでどのように取り上げられているかをみると、前向きにその意義を見出そうとしていると思われる見解と、批判的に懸念するものと思われる見解がありますので、それを簡単に整理して、その見解を参考に議長提案の意義的なものについて考えてみたいと思います。
◯批判的に懸念している思われる見解としては、まず、新制度は来年4月に始まるため、年明けになれば、業界団体が外国人労働者の受け入れに向けて技能を測る試験などを実施するようなので、そういう時期に国会で議論しても遅い、それではただの茶番劇にならないか。また、国会報告が、政府与党によるアリバイ作りに使われてはならない、形ばかりで終わらせては、国会の存在意義も問われるだろうなどと懸念を示し、制度が不明確であれば、改めて本格的に議論すべきだ、政府からの委員会報告を受けてその質疑の機会をどう生かすかなどと課題を呈しているような見解があります。
◯前向きな見解として、議長提案は、法律の施行前に政府から政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告し、委員会で質疑ができる環境を整えるということで国会の行政監視機能を利かせることに主眼があったとし、この提案の趣旨を生かせるかどうかが国会と政府の関係の健全化に向けた試金石となるというような見方があり、また委任立法は各国に共通の傾向となっているが、欧米では一般に「議会拒否権」と呼ばれている、議会が政省令を審査し不適切と判断すれば拒否できる制度があり、この議長提案が、そのような画期的な改革につながる可能性のある内容を含んでいると評価するような見解もあります。
2 報道記事では議長提案についてその意義を認めようとする前向きな評価と懐疑的な評価がありますが、ここでは、形骸化していると指摘される議会の審議機能等の充実という観点から「議長提案の意味するところ」について考えたいと思いますので、前向きに評価する見解を参考に、議長提案の意味するところは国会の行政監視機能の発揮、「議会拒否権」という議会が政省令を審査し不適切と判断すれば拒否できる制度のような画期的な改革につながる可能性のある内容を含んでいるものと位置付けた上で、その提案が現状において可能な提案かどうかを考えてみたいと思います。
3 報道記事にみられるような前向きな意義があるものとして議長提案を理解し、それが実現されていくことは望ましいことは言うまでもありません。しかしながら、議長提案をそのまま議会の行政監視機能充実に向けた契機となるものとして期待したり、委員会の新しい審議形態の道が拓ける可能性として捉えることは、「希望的評価」で終わるのではないかという懸念が生じてきます。それは、議長提案を受けた政府報告・質疑を行う委員会を開会すれば、それで既に終了した法律案審議における野党からの批判は帳消しになり、さらに法律案審議において全うできなかった審議の質を補充する措置になると評価しようとすることも含めて、議会政治の現状から目を背けることになってしまうのではないかという懸念が生じるからです。
4 何に目を背けるのか。それは、まず議長提案の意義を実現するためには障害があり、その障害は議会内部で改善することのできるもので、つまりは、議長提案の意義を実現するかどうかはそれを受けた議会内で自らできるはずの変革が伴われない限り不可能であるという自らの責任に目を背けることになるのではないかと思われます。そして、議長提案を歓迎して受け入れるのであれば、その変革を行うことにも手をつけなければ、議長提案それ自体をその場しのぎの対応ということにしてしまうということを認めなければならないのではないでしょうか。
5 また併せて、委員会を開会して政府に報告させて質疑を行うだけではなく、野党質疑があれば当然異論が出てくるでしょうから、その異論に対し、委員会としてどう整理がなされ、その結果を出していけるのかも検討されなければならないと思います。委員会における法律案審議では、異論については否決という「委員会の意思決定」ができるのですが、法律案審査の終了した委員会質疑ではそれに代わるものがないのは当然ですが、異論が出ても聞き流すだけというのであれば、開会されたその委員会の性格はどう考えればよいのでしょうか。報道記事にもあるように「茶番劇」、「政府のアリバイづくり」の委員会ということなってしまいます。
議長提案の真意がそこまでを意図しているかどうかはわかりませんが、報道記事にあるような前向きに評価する見解からはそう考えられるのではないかと思われますし、議長提案はそこまでのことを要請しているものだと理解すべきではないでしょうか 1。そういう要請でないと理解するならば、「入管法改正案」審議の際に野党から議長に対してなされた要望を受けて議長が収める形でもあった議長提案の経緯を軽視することになるのではないでしょうか。
6 また、「法制度の全体像について、国民に知らしめ、その理解をいただきたい」との議長提案は何を意味することになるのでしょうか。国民に知らしめるとはどういうことなのでしょうか。報告するだけで足りるのであれば、わざわざ委員会の場を利用しなくてもよいのではないでしょうか。「その理解をいただきたい」とはどういう意味でしょうか。ただ報告、公開しましたということを理解してくれというのでしょうか。
ここでの「国民に知らしめ」や「理解をいただく」とは、報告に対する質疑を行い、そこで国民が理解してくれるような内容ある議論を行うということであり、それは、野党から異議が出た場合は聞き流すだけでなく、委員会としてどのように整理できるのか、それも問われているという意味だと捉えるべきではないでしょうか。施行前の法制度に対する質疑において出てきた異論を聞き流すだけでは、立法府の機関としての責任は果たせないのではないでしょうか。それに対して委員会の意思としてはどうするのかを国民に提示する責任があるのではないでしょうか。委員会において整理できるということは、委員会としての結論を出すということと同じ意味にもなります。
7 ここでいう結論とは、委員会としての意思決定です。議長提案によって開会される委員会では、野党の異論に対して採決というような形で委員会としての意思決定はできません。野党は政府に対して異論を示し、それに対して政府から答弁がなされるだけです。答弁の中には、善処する、今後または次の改正時までに検討するなどのやり取りはあるでしょう。しかし、それを異論を表した野党が納得すればまだしも、納得できない答弁の場合、異論を聞き流すだけで、それをもって国民に理解をいただける質疑内容になるのでしょうか。確かに、委員会における報告、質疑、答弁は会議録に残ります。法律施行前に法律の概要を委員会で政府から直接確認できた、野党も法律施行前に異論を呈し国民の前に明らかにできたということで顔がたつかもしれません。しかし、その程度の成果で野党は満足することになるのでしょうか。その程度なら議長提案によらずとも、与野党合意すればいつでも開会できる内容の委員会ではないのでしょうか。
委員会の正式な意思決定という形であれば、委員会の決定として納得しなければならないし、国民にも委員会の意思として理解を求めることができる内容になるのではないでしょうか。ここでいう納得するということは、委員会の意思決定がなされたことを認めることです。議案に対して質疑段階、採決前までは反対していたとしても、委員会、本会議において議決された結果は正式な決定であることは認めなければならないことはいうまでもないことです。反対したのだから従わないというわけにはいかないものでしょう。多数意思により、野党からの批判、異論が委員会の意思でないとされた場合でも、それは委員会の正式な意思であり、国民にも委員会の正式な意思として提示できるものだと思います。それを多数の横暴だと批判することはできないと思います。多数の横暴という批判が適切な批判となるのは、委員会の審議過程における審議時間など審議過程の質の程度が問題とされるときだと思います。
8 繰り返しになりますが、委員会質疑において異議が出た場合、委員会においてどう整理し、結論を出すことができるかが、議長提案を受けて開会され委員会の大きな課題ではないでしょうか。野党の異議を捨て置くということであれば、そもそも野党としては、法律案審議の際には採決日程ありきとか、白紙委任だと批判し、与党の委員会運営に抗議して本会議を見送るよう議長に申し入れを行ったにもかかわらず、何のために委員会に出席して質疑を行ったのかということにもなります。政府・与党の議長提案はそのように理解すべきであり、その趣旨で委員会質疑を行うことが与野党の責務ではないでしょうか。議長提案がそこまでを要請するのではないとするのであれば、野党はこの議長提案を拒否すべきであったと思います。そうでなければ、本会議に出席しても批判されない理屈が欲しかっただけということになるのではないでしょうか。 そして議長提案は与野党のもつれを解消して両者の顔が立つようにする手段という意味しかなかったということにもなるのではないでしょうか。
9 少なくとも、議長提案が、政府・与党にとっては、国民的争点となる重要問題の審議が不十分だとする批判を免れるためのものであるとか、野党サイドとしては、この提案を受け入れることで、意に反して不十分な審議過程しか残せなかったことの、議会(委員会)審議における野党の責任を免罪するということにならなければと思います。
また、立法府の問題として、現在までの政府委任立法と審査の在り方は立法府の形骸化につながると指摘されてきているなか、議長提案の趣旨がいかなるものであろうと、この提案による措置が立法府形骸化の歯止めの第一歩にすることができなければ、今後、政令委任事項が多岐にわたる法律案審議の際、従来どおりの審議形式(法律案審議段階では法律成立後の政令の内容がわからない)に大義を与える道を開く契機となるという懸念が生じるかもしれません。
10 ここでは思い浮かぶいつくかの問題を列記して、今後の検討課題にしたいと思います。そして、あえて批判的に考えてみることが、議会の形骸化と改革の方向や議会政治の現状を把握できるのではないかと思いますし、批判的に評価する中に議会形骸化の一因を発見でき、形骸化是正のひとつの道が発見できればと思います。
報道では、2019年1月23日に法務委員会の閉会中審査の委員会を開会して議長提案による政府報告、質疑が行われるようです。議長提案を受けて開会される委員会では、下記の懸念が払拭されるような実のある議論が行われ、今後、それがどのような形で議会審議機能充実につながって行くのか、そして、「委任立法と議会」という課題について委員会の新しい審議形態の道が拓ける可能性が見出せるか、などという観点から注目したいと思います。
(問題点)
1 (政令内容の修正ができるのか。あるいは委員会の見解を形として反映できるかについて。)
委員会において政府から具体的に政令内容の報告・説明が行なわれて、委員会が納得できない内容を修正できるのでしょうか。政府は政令内容を修正する用意はあるのでしょうか。野党が考えを主張しても反映できないということであれば(与野党で合意すればという意味であることはいうまでもありません。)、その委員会は、単に政府からの報告があっただけということであり、それだけであれば、わざわざ議長提案によらずとも、施行前の確定した時期に、通常の委員会を開会し与野党あるいは野党から要求すれば同じレベルの政府からの報告が実現するし、報告がなくても国政調査案件に対する一般質疑のなかで政府に確認し、異議を表明し批判することも可能であり、必要なら資料要求の形でも政令の内容は知り得ることだと思います。議長提案がなされたから、そのための委員会を開会しただけという結果になるのであれば、議長提案から期待される、委員会審議機能充実や、「委任立法と議会」という課題について委員会の新しい審議形態の道が拓ける可能性を消失させる結果となるのではないでしょうか。
2 (修正に代わる附帯決議などについて)
政令内容の修正が不可能であれば、議案審議における附帯決議に変わるようなもので「その場を収める」ということが可能なのか、そして、そのような対応は政府・与党にとって可能なのかどうかです。附帯決議は修正と異なり議案内容を変更するものではないので、附帯決議的なものは「やればできるもの」だと思われます、野党がそれでもよいとし、与党が応じるのであれば。それは附帯決議と異なり審議に附随した性質のものではないという違いがあるだけだと思います。委員会の意志が表明されるのであれば附帯決議の効果とさほど変わりはないのではないかと思われます。そもそも附帯決議は、法律的効果はなく、行政がその法律を執行する際の、法律案審議が行われた「委員会の要望でしかない」という性質のものではありますが。
そして報告があり質疑が行われた後、委員会における何らかの評価がどのような形で反映されていくか、その観点から検討してみることも議長提案を受けて開会されることになる委員会の性質と、それが今後の委員会審議機能充実に向けた契機となるかどうかの試金石として位置付けることができることができるかもしれません。
3 (委員会決議について)
附帯決議は議案審査に附随した段階における決議であるので、議案審査は終了しており附帯決議的なものも「なじまない」ということであれば、議案審査から離れても可能な、委員会決議をおこなうことが可能かどうかです。委員会決議ともなれば議案に「附帯する」決議とは異なり、政府に対する委員会の意思表明はさらに「強い」効果を有する性質のものであるため、これを安易に政府・与党は受け入れることが可能かどうかという問題があります(法律案審査終了後、関連の委員会決議を行うことは可能ですが、事例は多くないと思われます。)。
4 (委員会の見解を反映できない場合について)
野党としては、議長提案を受けて開会される委員会で、政令の内容などの報告を受け質疑を行って異議があればそれを主張しておくだけでよいのでしょうか。先に行われた委員会審議では、どういう内容を政令にするのか、その内容に関係した審議が必要だったのではないでしょうか。その審議では、政令内容及びそれに関係する事項を修正出来る可能性は「法律案審議手続きの法規上の可能性として」残されていたわけであります。しかし、委員会審議終了後に、法律が成立し施行することが決まった段階で、政令の内容について報告が行われ質疑を行ったとしても、それは議案審査ではないのはいうまでもなく、そうであれば野党の見解をその政令の内容に反映する可能性はゼロの「質疑」ということになります。先の報道記事にあるように、「議会拒否権」と呼ばれている、議会が政省令を審査し不適切と判断すれば拒否できる制度があれば別ですが。議長提案を受けて開会されるであろう委員会において、野党としては異論があるものについて、ただ委員会で声高にその不適切等を指摘し、政府を批判する場にできれば良いのでしょうか。
5 (委任立法に対する野党の対応)
今後、政令委任事項が多い法律案審議の際、野党は今回と同じような対応を受け入れることができるのかでしょうか。
今回の報告を受けて開会される委員会質疑で野党として得るものがなければ、あるいは委員会審議機能充実の契機になる期待が生じなければ、野党は今回の対応を評価しなおさなくてもよいのでしょうか。法律は成立しており、委員会で報告する内容はすでに確定しているもので、その報告・質疑は法律案審議ではないため、委員会における報告内容についての見解、異論を何らしらの形として反映できる可能性はなく、議長提案により政府から報告するだけということなら、今回のような対応の繰り返しはかえって議案審議の形骸化になってくるかもしれません。
6 (議会形骸化からの問題点等について)
白紙委任だと批判していた政令内容について委員会で異議があった場合、それをどういう形で反映できるのか、法律案審議ではないため修正もできるはずがない、附帯決議的なものも委員会決議もできない、そして、委員会の意思を何らかの形で反映することの可能性が一切ないということであれば、そこで行われた報告・質疑はいわゆる「ガス抜き」、「一応丁寧に、施行する前に報告しました」という形づくりの委員会でしかないという批判が生じるかもしれません。野党から質疑時間が十分でない審議日程と異議のあったすでに終了した議案審議を、関係政令を施行前に委員会に報告するということで、議会において最終的には「丁寧に仕上げた」という形をつくりあげ、一件落着ということにしておくだけではないか、などの批判も生じるかもしれません。それは、かえって議案審議形骸化にならないでしょうか。委員会において質疑を行う過程で生じた問題点などをどのように取り込んでいくことができるのかということも大事な点だと思います。また将来的に可能になるような制度改正をするというのなら、今後の議会における審議形態の変革の契機となるのではないかと思います。
7 (議会先例としての意義について)
今回の議長提案による委員会が、「ただ委員会を開会しただけ」の結果に終わったとしても、法律施行前に関係政令の内容について委員会に報告をして質疑を行ったという先例は残り、その結果とは離れて「一人歩き」を始め、「はじめの第一歩」としての先例になっていく可能性はあり、「委任立法と議会」という課題から新たな委員会審議形態の道が拓ける可能性は残ります。そして、その可能性を形あるものとしていくことができるかどうかが議会審議機能充実に向けた大きな課題だと思われます。
(最後に)
前述したことを繰り返しますが、少なくとも、この提案が、政府・与党にとっては、国民的争点となる重要問題の審議が不十分だとする批判を免れるためのものであるとか、そして、野党サイドとしては、この提案を受け入れることで、意に反して不十分な審議過程しか残せなかったことの、議会審議における野党の責任を免罪(厳しく言えば、先の委員会審議は過去のこととしてしまう。)するということにならなければと思います。
そして、立法府の問題として、現在までの政府委任立法と審査の在り方は立法府の形骸化につながると指摘されてきているなか、今回の議長提案による措置がその歯止めにもなり得ないとなれば、あるいは何らかの成果もなければ、今後、政令委任事項が多岐にわたる法律案審議の際、野党から白紙委任だとする批判があったとしても今回の対応がその批判を解消する逃げ道とされるのであれば、従来どおりの審議に大義を与える道を開くことになるという懸念が生じるかもしれません。
第196回国会閉会後に大島衆議院議長は以下の談話を出されました。その談話の趣旨からは、第197回国会の「入管法改正案」についての議長提案は、議会の行政監視機能、審議機能等の向上に資することを意図されていると思われるのではないでしょか。
Notes:
-
第196回国会閉会後に大島衆議院議長は以下の談話を出されました。その談話の趣旨からは、第197回国会の「入管法改正案」についての議長提案は、議会の行政監視機能、審議機能等の向上に資することを意図されていると思われるのではないでしょか。
衆議院議長談話(今国会を振り返っての所感)
まず、今般の西日本の豪雨災害により亡くなられた多くの方々に対し、心より哀悼の意を表しますとともに、御遺族の方々にお悔やみを申し上げます。また、被災された方々に対し心よりお見舞い申し上げます。衆議院では、10日の本会議で決議を行いました。先日の台風12号により、被災地の皆様には、二次災害の危険など更なる過酷な状況が続きますが、政府におかれましては、この決議の趣旨を十分尊重して、被災者の方々に寄り添いながら、対応に万全を期していただきたいと思います。
先般の通常国会は、1月22日にはじまり、7月22日まで、延長を含めて182日間の会期となりました。
1.この国会において、①議院内閣制における立法府と行政府の間の基本的な信任関係に関わる問題や、②国政に対する国民の信頼に関わる問題が、数多く明らかになりました。これらは、いずれも、民主的な行政監視、国民の負託を受けた行政執行といった点から、民主主義の根幹を揺るがす問題であり、行政府・立法府は、共に深刻に自省し、改善を図らねばなりません。
2.まず前者について言えば、憲法上、国会は、「国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関」(憲法41条)として、「法律による行政」の根拠である法律を制定するとともに、行政執行全般を監視する責務と権限を有しています。これらの権限を適切に行使し、国民の負託に応えるためには、行政から正しい情報が適時適切に提供されることが大前提となっていることは論を俟ちません。これは、議院内閣制下の立法・行政の基本的な信任関係とも言うべき事項であります。
しかるに、(1)財務省の森友問題をめぐる決裁文書の改ざん問題や、(2)厚生労働省による裁量労働制に関する不適切なデータの提示、(3)防衛省の陸上自衛隊の海外派遣部隊の日報に関するずさんな文書管理などの一連の事件はすべて、法律の制定や行政監視における立法府の判断を誤らせるおそれがあるものであり、立法府・行政府相互の緊張関係の上に成り立っている議院内閣制の基本的な前提を揺るがすものであると考えねばなりません。
3.また、行政・立法を含む国政は、「国民の厳粛な信託によるもの」であり(憲法前文)、民主主義国家においては、国政全般に対する国民の信頼は不可欠なものであります。
にもかかわらず、行政執行の公正さを問われた諸々の事案や、行政府の幹部公務員をめぐる様々な不祥事は、国民に大いなる不信感を惹起し、極めて残念な状況となったのではないでしょうか。
4.政府においては、このような問題を引き起こした経緯・原因を早急に究明するとともに、それを踏まえた上で、個々の関係者に係る一過性の問題として済ませるのではなく、深刻に受け止めていただきたい。その上で、その再発の防止のための運用改善や制度構築を強く求めるものであります。
5.以上のような問題を生起せしめた第一義的な責任は、もちろん行政府にあることは当然でありますが、しかし、そのような行政を監視すべき任にある国会においても、その責務を十分に果たしてきたのか、国民の負託に十分に応える立法・行政監視活動を行ってきたか、については、検証の余地があるのではないでしょうか。国会議員は、私自身も含め、国民から負託を受けているという責任と矜持を持たねばなりません。このような観点から、最近、各党各会派や議員グループから、国会改革に関して具体的な提言がなされていることも、衆議院議長として、承知しているところであります。
今国会を振り返り、私たちは、国民から負託された崇高な使命とあるべき国会の姿に思いをいたし、憲法及び国会関係諸法規によって与えられている国会としての正当かつ強力な調査権のより一層の活用を心掛けるべきであります。そして、必要とあれば、その実効性を担保するため、それら国会関係諸法規の改正も視野に入れつつ、議会制度協議会や議院運営委員会等の場において、各党各会派参加の上で、真摯で建設的な議論が行われることを望むものです。
(平成30年7月31日) ↩







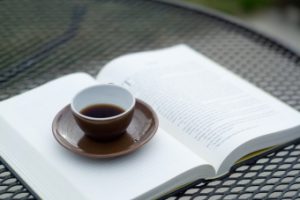










最近のコメント